『西郷どん』は第57作目のNHK大河ドラマとして制作され、2018年1月7日から全47話が放送されました。
リアルタイムでは見ていませんでしたが、少し前に「NHKオンデマンド」というNHKの大河ドラマやドキュメンタリーが見られる有料動画サービスに加入したので一気見することにしました。

大河ドラマ 西郷どん-SEGODEN-の概要と感想
配役や脚本について
物語の主人公である西郷隆盛(さいごう たかもり)について知っていたのは、学生の頃授業で習ったことと、子供の頃大好きだった「漫画 日本の歴史」で得た知識くらいでした。
しかし、『西郷どん』を見るまでに、同じ時代を描いた『篤姫』や『龍馬伝』を見ていたので、全てが史実ではないものの、幕末から明治にかけての知識は最低限持っていました。
主人公の西郷隆盛役に抜擢されたのは<鈴木亮平>さんです。
鈴木亮平さんに関しては、最初は体が大きいところ以外は西郷隆盛のイメージが全くなかったのですが、年齢に応じた役作りが素晴らしく(凄まじく?)、壮年期から晩年までに多分30キロ近く増量しているのではないかと驚嘆しました。
『坂の上の雲』で正岡子規を演じた<香川照之>さんの役作りにも、鬼気迫るものを感じました。役者さんって本当に凄いですね。
鈴木さんは大河ドラマ初出演なので、”被り”がない点もよかったです。大河ドラマは作品や人物は違っても、同じ俳優さんを使うことが多いので、面白いと同時に少し混乱してしまいますから(笑)。
例えば、『篤姫』では小松帯刀役だった<永山瑛太>さんが、『西郷どん』では大久保利通を演じていたり、『龍馬伝』では後藤象二郎役だった<青木崇高>さんが、『西郷どん』では島津久光を演じていたりします。
そのほか、小さい役柄でも、沢村一樹さんが『篤姫』で小松清猷、『西郷どん』では赤山靱負を演じていました。両方とも俊才なのに早死にでもったいなかったですね。
原作は林真理子さん、脚本は中園ミホさんと、女性的な話作りと視点で西郷隆盛を描いた作品になっていました。しかし、史実からかなり離れた展開もあったので、当時は賛否両論だったのではないかと思います。
平均視聴率は12.7%でした。後に異次元の平均視聴率(関東8.3%、関西7.0%)を叩き出した『いだてん』が放送されるまでは、『花燃ゆ』『平清盛』に続く歴代ワースト3位の数字だったようです。ただし、今の時代は単純に視聴率イコール人気ではありません。
全話を見ての個人的な感想は、ガチガチの大河ドラマではなく、『龍馬伝』と同じようにフィクションの多い時代劇ドラマという風にとらえれば、普通に面白かったです。どちらかといえば、韓国時代劇ドラマに近いと思います。
西郷と大久保の親交・決別
それではドラマの内容について少し。
この物語は、下級藩士として生まれた西郷小吉(後の隆盛、通称は吉之介、善兵衛、吉兵衛、吉之助)の人生を描いています。
西郷は、賢君として名高い開明派大名・島津斉彬に見いだされ、数多くの働きをします。しかし、時勢や斉彬の死によって二度も島流しにされるなど、多くの苦難に直面。それでも、西郷は「民のために尽くす侍になる」ことを目指し、困難を乗り越えていくのです。
個人的に印象に残っているのは、盟友である大久保正助(後に一蔵→利通)との親交や決別、そして薩摩隼人の心意気です。
征韓論(明治6年の政変)で袂を分かったものの、新政府樹立まで薩摩藩の両輪(今作では小松帯刀の印象が薄かったので)として活躍してきた西郷と大久保。歳は3つ違うものの、同じ郷中で生まれ育ち、切磋琢磨しながら成長した二人の英雄について多くを知ることができました。
全てをリセットして1を創り出すことにかけて天賦の才を持つ西郷と、創り出された基礎を装飾し整備することにかけては古今無双の大久保という対照的な二人。それぞれの国や民に対する想いやそれを実現させるための手段が少しずつズレていくことに、寂しさを感じたものです。
お互いがお互いの能力や性格を認めているのに、コミュニケーション不足だったのか、離れていくことを留めることができなかったのは、やっぱり二人が”薩摩隼人”だったからなのでしょうか。薩摩には「男は三年に片頰」という言葉があるくらいですからね…。
岩倉使節団の一員として西欧諸国を見て回り、日本との圧倒的な国力の違いや強国から一つの国として認められていないことを知った大久保が、「殖産興業」「富国強兵」を急ぎ、創業→内治整理→守勢を30年で成し遂げて強国に負けない強い日本をつくろうとしたことは間違いではありません。
ですが、この時の日本には正論と分かっていても「変われない」「変わりたくない」人(武士→士族)がたくさんいたのです…。
西南戦争と西郷・大久保の最期
不平不満が溜まった士族は、征韓論で敗れ鹿児島に帰った西郷のもとに集まり始めます。
その中には、政府の中で今後重要なポストを担う可能性もあった桐野利秋(中村半次郎)や村田新八、篠原国幹らの姿もありました。幹部連中の一部については、単純に西郷を慕ってついてきたようです。
西郷は、この変われない人々のために、何とかこれからの時代を生きる術や心を身に付けさせようと奔走。しかし、不平士族の行動を警戒する新政府側の動きなどもあって、結局は日本国内最後の内戦「西南戦争」へとつながっていくのです。
これまでは、西郷自身は反乱を起こす気は全くなく、不平士族たちの勢いに押されて神輿として担がれることになったというのが定説でした。しかし、数年前にNHKか何かの番組で、西郷自身も行動を起こすことを考えていたという説もあると放送されていました。
その根拠は、桂久武(ハンバーグ師匠)に宛てた書簡に「起つと決した時には天下を驚かす」と書かれていたことだそうです。ただ、これに関しては、憂慮していた対ロシアについてのこととも考えられています。
戦いは、圧倒的な兵力や武装の違い、1870年に誕生した電報による戦況把握と先を読んだ兵力補充などによって、西郷軍は敗北を重ねます。
最後は、数百人まで減った仲間たちと宮崎・鹿児島の山岳部を踏破し、10日以上かけて故郷鹿児島へと帰還するものの、政府軍の総攻撃を受けました。桐野は額に銃弾を受けて戦死し、村田と西郷は自決という結果に終わりました…。
最後の戦いの前に、村田のアコーディオンに合わせて仲間たちで楽しく歌ったり踊ったりしていたところがとても印象的でしたね。村田新八は史実でも従軍中にアコーディオンやコンサティーナを持ち歩いていたとのことで驚きました。
明日訪れる確実な死を前に、自分ならどういう気持ちになるのだろうと考えました。
新しい時代に適応することができなかった自分のようなものと一緒に、ずっと尊敬してきた維新の英雄である西郷隆盛が死んでくれるのなら、もう何も怖くないと思うのではないでしょうか。
現代では、戦時の危険思想に通ずると批難する人が多いかもしれません。しかし、「士は己を知る者の為に死す」という言葉もありますし、今の世の中でも自分の命をかけられるような立派な人間が少ないだけなのではないでしょうか。
西郷自身はまだやりたいことがあったのか、それとも新しい時代を創り変われなかった人たちと一緒に死んであげることができて本望だったのかは、今となっては知る由もありません。ですが、征韓論のこともあるので、個人的には後者ではないかと考えます。
一方、盟友を失った大久保はその後、麹町紀尾井町清水谷で不平士族6名によって暗殺されてしまいます(紀尾井坂の変)。
西郷と違って、大久保は政府の中心として国を豊かにそして強くするために、まだまだやらなければならないことがあったので、無念だったでしょうね…。
西郷を殺したというイメージがつきまとい、冷酷で血も涙もない人物のように思われがちな大久保ですが、政治家としての能力は日本歴代でも5本の指に入る英雄です。また、西郷に対する想いも、人々が考えるようなものではなかったのではないかと個人的には思います。
魅力的な脇役・大山綱良
『西郷どん』では、西郷や大久保以外にも魅力的な人物がたくさんいましたが、僕は大山さんが好きでした。
作中の大山綱良(通称は正圓、角右衛門、格之助)は、西郷より二つ年上で、ユーモアとやる時にはやる”凄み”を持った人物です。
皆でわいわいしている時はエスプリの効いた会話で周りを盛り上げ、有馬新七ら過激派を粛正した寺田屋騒動では、仲間たちを殺すことになっても武士としての使命を全うする”覚悟”を見せてくれました。第23回で、寺田屋へ向かう前の「行こかえ」というセリフには鳥肌が立ったものです。
大山さんは、薬丸自顕流の剣術を極めた小太刀使いの達人だったそうです。
大山さん、本当にかっこいい!
大山さんの最期は、県令でありながら逆賊である西郷らを支援した罪を問われての斬首でした。しかし、文句を言いながらも西郷を助けてあげる大山さんの優しさに、心が温かくなった視聴者も多いはずです。
wikiを見ると、処刑された1877年に従5位の官位を剥奪されていますが、西郷や桐野、村田らと同じように名誉を回復されているのでしょうか。気になるところです。
最後に
以上、『西郷どん』を見た感想をダラダラと書き連ねてみました。食事をとりながらだったり、雑務をしながらだったりと”ながら見”が多かったので、細かいところは見られておらず、間違っているところも多いかもしれません。
『西郷どん』は、史実に忠実ではないファンタジーな要素もたくさん入った作品でした(これはないわぁというシーンも多々あり)。しかし、笑いあり涙ありの素敵な作品だったと思います。歴史を学ぶというよりは、人間の生き様を学ぶという感じでした。
結論として、薩摩隼人はやっぱり不器用でかっこいい!




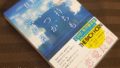
コメント