アドミニストレータによってシンセサイズされたユージオは青銀の甲冑に身を包んだ姿で現れました。
彼は三十二番目の整合騎士“ユージオ・シンセシス・サーティツー” へと変容し、キリトたちの前に立ちふさがったのです。

第二十一話「三十二番目の騎士」のあらすじと感想①
無二の親友でありアインクラッド流の師弟関係でもあるキリトとユージオ。
避けられない戦いの中、二人が初撃として繰り出したのはアインクラッド流片手直剣突進技「ソニックリープ」でした。
第二十一話はキリトとユージオの師弟対決がメインとなる回です。
この回からオープニングアニメが少し変化し、特にキリトとアドミニストレータの戦いのシーンでは動きや表情が細かく描かれ、非常に印象的でした。

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
キリトとユージオの激しい剣戟
キリトとユージオが同時に放ったソニックリープは威力もスピードも全く同じでした。
同じタイミングで同じ技を放つのだから当たり前だと思う人もいるかもしれません。
しかし、キリトは技をただ出しただけでなく、足の蹴りと体の捻り、そして腕の振りによって秘奥義に三重の加速を与えています。この技術はまだユージオに伝えていないものでした。
キリトはユージオがキリトの見ていないところで、毎日何百回も “愛剣の声” が聞こえるようになるまで地道に愚直に剣を振り続けこの技術を習得したのだろうと推測しています。
ソニックリープが終了した瞬間、高速の近接戦が始まりました。
右上段斬りから右の薙ぎ払い、左斜め斬り下ろしを経て二度目の鍔競り合いに移行する二人。
「本気で剣を交えたら、俺とお前のどっちが勝つのか、ってな。……正直に言えば、いつかお前には追い抜かれるだろうって、そう思ってた」
アニメではカットされていますが、原作でキリトはこのセリフの後に重要な言葉を投げかけています。
「……でも、いまはまだ、その時じゃない。俺のことも、アリスのことも、ティーゼやロニエたちのことも、カーディナルのことも忘れてしまったお前じゃ、俺には勝てない。それをいま、証明してやる」
このセリフはすごく重要だと思うのになぜカットしてしまうのでしょうか…。
アインクラッド流体術《弦月》

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
――これはお前に見せたことのない技だ。
キリトが放ったのはアインクラッド流体術の後方宙返り蹴り技「弦月(げんげつ)」でした。後ろに倒れこみながら全身をコンパクトに回転させ相手を蹴り上げる技です。
アニメではこの弦月でユージオの右手を蹴り上げ、青薔薇の剣が天井に刺さるという簡略化された展開になっていますが、原作ではより詳細な攻防が描かれています。
原作ではキリトは最初ユージオの下あごを狙いました。
一方、キリトの狙いを察したユージオは剣の柄頭(つかがしら)でキリトの右足を迎撃しようとします。
逆手握りでの柄当てはアンダーワールドには存在するはずのない実戦的テクニックであり、旧SAO時代でもよほど対人戦に慣れたプレイヤーでなければ使わない高等技術でした。
キリトはこれを見抜き、スキルがファンブルしない僅かな間、足の動きを止めてからユージオの右手の甲を蹴ります。そして着地と同時に単発ソードスキル「スラント」を繰り出しました。

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
「バースト・エレメント」
剣を失ったユージオは5個の「風素」を同時に炸裂させ、爆発的な突風を発生させました。
キリトは暴風に翻弄されつつもなんとかダメージを最小限に抑えます。
原作では両者とも暴風に押し流される描写がありますが、アニメではユージオが動かないという不自然さが見られました。いつもながら今回の製作陣はこういう細かいところが雑ですね…。
アリスの疑問とキリトの確信
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
「……あの者が、本当に、お前の相棒のユージオなのですか」
ユージオの戦いぶりに違和感を感じたアリスがキリトに問いかけます。
本来、心意技や武装完全支配術、秘奥義や神聖術の要諦は長い研鑽を経て初めて身につくものです。それをたった数時間前に整合騎士となったユージオが習得している事にアリスは疑問を抱いたのです。
アニメではこの後すぐに「私が相手をしましょうか」というアリスのセリフになりますが、原作ではキリトの内面描写がより詳細に描かれています。
キリトは「……ユージオだ」と答え、アドミニストレータがユージオそっくりの偽物を用意した可能性や、ユージオが短時間で様々な技や術を習得した理由は分からないながらも目の前の整合騎士が自分の相棒にして親友であるユージオ本人だと確信していました。
そうでなければ、誇り高い青薔薇の剣が偽物などに従うはずがない、と。
この時点でキリトは自分の全てを剣に乗せてユージオに撃ち込むことを決意します。
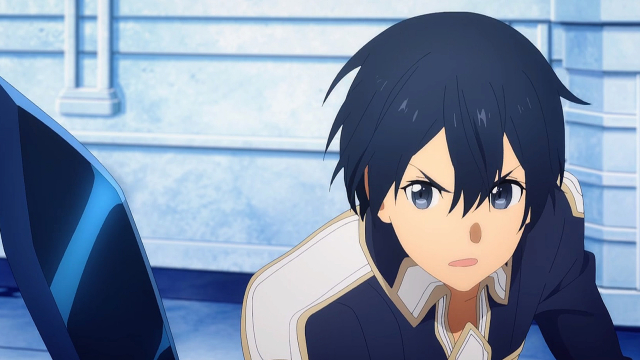
©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
――頼むぜ、相棒。
――戦いが全部終わったら名前をつけてやるから――俺に、力を貸してくれ。
あらゆる雑音が、背景が、温度までもが遠ざかる。世界には俺と黒い剣、ユージオと青薔薇の剣しか存在しない。この瞬間が訪れることを、俺は二年前から心の奥底でずっと畏れ、そして待っていた。
――行くぜ、ユージオ!!
SAO アリシゼーション・ユナイティングより
僕は原作のこの場面の描写がすごく好きなんですが、アニメではただ構えているだけで緊迫感や高揚感が全く感じられませんでした。
この瞬間を境に秘奥義を使わない接近戦が始まります。キリトとユージオは両者とも剣を両手で持ち、より激しい戦いへと突入していくのでした。
戦闘シーンの解釈

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
戦闘の演出で特に気になったのはキリトの上段斬りがユージオの左肩口を捉え、同時にユージオの攻撃もキリトの左肩口を捉えているシーンです。
宙に舞う金属の細片に、真紅の飛沫が入り混じる。手応えからして深手ではないが、ついに俺の剣がユージオの体を切り裂いたのだ。
友を傷つけたと認識した瞬間、俺も同じ場所に、我が身を斬られたような痛みを覚える。避けがたく顔が歪むが、ここで手を止めるわけにはいかない。垂直斬りが床に達した瞬間に手首を返し、全身のバネを使って追撃の斬り上げを――
SAO アリシゼーション・ユナイティングより
原作を読むと、このシーンはキリトの内面の葛藤を象徴的に描いていると解釈できます。
無二の親友であるユージオを傷つけてしまったことが、自分自身が 同じ場所を斬られた “かのように” 辛く苦しいというキリトの心情を表現していると思うのです。
しかし、アニメ制作陣はこの描写を文字通りに解釈し、キリトも物理的に斬られたかのように描いていました。
これまでのエピソードでも原作の意図を十分に汲み取れていないと思われるシーンが散見されました。
今回の解釈の違いも含め、制作陣が『ソードアート・オンライン』という作品の本質や魅力を十分に理解しているのか、疑問を感じざるを得ません。
バルティオ流《逆浪》とソードスキルの名称

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
激しい接近戦の中、キリトは体当たりでバランスを崩したユージオに「スラント」を繰り出します。
すでに左肩に傷を負っているユージオの右肩にこの一撃が当たれば剣を振るのが困難になると計算しての一撃でした。
体勢を崩し、右後背を晒したユージオに反撃の余地はないと思われましたが、緋色の閃光を迸らせながらユージオは両手剣単発技「バックラッシュ」を放ちます。

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
このソードスキルは敵に背後を取られた状態から反時計回りに猛然と回転し、逆転の一撃を狙うカウンター技です。
原作では二つの技が激突して両者の剣が大きく弾き飛ばされた後、キリトとユージオが共に単発上段垂直斬り「バーチカル」を発動させて鍔迫り合いに移行します。
しかし、アニメでは技が終了せずにそのまま鍔迫り合いになっています。
「……今の技、名前はあるのか」
ユージオに教えた覚えがない「バックラッシュ」について訊ねるキリト。
「……バルティオ流、《逆浪(げきろう)》」
バルティオ流は、北セントリア修剣学院でユージオが仕えた上級修剣士ゴルゴロッソ・バルトーの流派でしたね。
アンダーワールドでは旧SAO時代の技が異なる名称で呼ばれています。
例えば、「スラント」はザッカライト流では「蒼風斬(ソウフウザン)」、「サイクロン」はセルルト流では「輪渦(リンカ)」、「バーチカル」はノルキア流では「雷閃斬(ライセンザン)」と呼ばれています。
記憶を失いながらも技の名前や使い方を覚えているユージオを見てキリトは新たな推測をします。
フラクトライトに挿入された敬神モジュールによって記憶の流れが遮断されているなら、現在モジュールが差し込まれている領域に存在した記憶を呼び起こすことでユージオの意識を取り戻させられるかもしれないと考えたのです。
剣を通じた魂の交感

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
「刃に込められたものは相手の魂にまで届く。俺は、そう信じる」
アドミニストレータの術を破るためには言葉だけではきっと足りないと考えたキリトは、剣を通して言葉以上のものをユージオに伝えようとします。
アニメのセリフ部分だけ聞くと、いきなりのくさいセリフに驚いた人も多いかもしれませんが、これは原作の文脈をカットしてつなげたためにやや言葉足らずな印象になっているのです。
俺は、鋼鉄の浮遊城アインクラッドに囚われたあの日から、たくさんの人たちと剣を通して語り合ってきた。アスナ、直葉、シノン、絶剣。この世界に来てからも、ソルティリーナ先輩やウォロ主席修剣士、エルドリエやデュソルバート、ファナティオら騎士たち。そして背後で戦いを見守るアリス。
仮想世界の剣は、ポリゴンでできたオブジェクト以上の意味を持つ。己の命を預けるがゆえに、刃に込められたものは相手の魂にまで届く。憎しみから解き放たれた剣は、時として言葉を超える交感を生み出す。俺は、そう信じる。
SAO アリシゼーション・ユナイティングより
原作では、キリトがこの後、型も技も戦術もない本能的な連続攻撃を仕掛ける描写があります。ただ速くひたむきに。
アニメではキリトがごちゃごちゃと言葉で説得を続けていますが、剣で語り合うと決意したキリトにこれほど多くの台詞は不要ではないかと感じました。
ひび割れゆく記憶の殻

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
また、アニメではユージオの視点で幼い頃の記憶が再生されますが、原作では激しい打ち合いの中で存在するはずのない幼いユージオとのチャンバラの記憶がキリトの脳裏に浮かぶという描写になっています。
一合剣を交えるたびに、不可視の殻がひび割れていくのを感じる。
いつしか俺は唇に荒っぽい笑みを浮かべている。そう、ずっと昔、こんなふうにユージオと無茶苦茶な剣戟、いやチャンバラをしたことがあったはずだ。修剣学院の修練場で、ではない。央都を目指す旅の途中でもない。そう、ルーリッドの村にほど近い草原や森で……剣の修行のつもりで、おもちゃに毛が生えたような手作りの木剣を……まるで子供のように、ひたむきに打ち合った……。
二年と少し前、森の中で出会ったばかりの俺とユージオが、そんなことをしただろうか?ひび割れているのは……俺の記憶………?
SAO アリシゼーション・ユナイティングより
アニメ化に際して原作と全く同じにする必要はありませんが、一ファンとしてはキャラクターの心情が詳細に描かれている部分などはできるだけ原作を尊重してほしいと思います。
アニメ版アリシゼーションの問題点は気合の入ったオリジナル要素をガツガツ加えようとしたり、逆に原作を忠実に再現しようとしたりするのではなく、原作の細部を読み飛ばしてストーリーの大筋だけを適当になぞっているように見える点です。
食べ物の描写以外では制作側の熱意があまり感じられないのが残念です。
ユージオの記憶回復と予想外の展開

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
剣戟の中で記憶が戻ったユージオ。
自虐的な仄かな笑みが印象的でした。

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
「エンハンス・アーマメント」
ユージオは物凄くオーバーな動きで武装完全支配術の “強化” 《エンハンス・アーマメント》を唱えます。
原作ではキリトが終戦の意思表示と思うほどゆっくりと床に剣を突き立てたはずですが、アニメでは完全に武装完全支配術を使おうとするモーションでした(笑)
それと、原作でユージオが唱えた式句は《リリース・リコレクション》、つまり “記憶解放” です。
アニメではなぜ “強化” にしたのか。何か理由があるのでしょうか。


©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
“解放” ではなく “強化” で完全な氷漬けになるキリトとアリス。
整合騎士になっても実力ではアリスより下のユージオが単なる “強化” で二人の実力者を氷漬けにするという展開は原作の設定との整合性に疑問を感じさせます。
キリトとアリスを動けなくしたユージオは昇降板で上階へと昇っていきました。
「……ごめんよ、キリト……アリス。僕を、追ってこないでくれ……」
キリトvsユージオ。
原作小説では大好きなシーンのひとつだったので、アニメでどのように表現されるのかと本当に楽しみにしたんですが、ビックリするぐらい残念な出来でした…。
原作を中途半端になぞるだけで細部の描写は全く反映されていないし、動きもお世辞にもかっこいいとはいえない上に見せ方も微妙。
前々からずっと思っていた事なんですが、今回の制作陣はこの『SAOアリシゼーション』という作品のどの部分を視聴者に伝えたいのでしょうか。
心情描写も少なく戦闘シーンも微妙。ストーリーも原作を10倍くらい薄めただけ。印象に残っているのは良い意味でも悪い意味でも第十話とエンディングアニメラストのキリトとユージオのハイタッチのところくらいでしょうか。
原作小説は本当に面白くて一期や二期に全く負けていません。それどころかアインクラッド編やマザーズロザリオ編と並んでSAOシリーズの中でも最高傑作の一つと評されるほどです。
そんな傑作をなぜこれほどまでに平凡な作品に仕上げてしまうのか…。
ここで強調したいのは、原作の質が低いのではなく、アニメの出来が “イマイチ” ということ。
Amazonプライムビデオ等のレビューで、原作を知らない視聴者がストーリーを猛批判しているのを見ると本当に心が痛みます…。
前監督の伊藤智彦さんはカットや改変を行いつつも、作品への愛と優れたセンスで時にはアニメの方が原作以上に面白く、感動的な作品に仕上げていました。
キャラクターの心情描写はもちろんのこと、戦闘シーンについても、絵自体は今の方がきれいかもしれないけれど、”魅せ方” が上手でソードスキルを使っているキャラクターの動きなんかがとにかくかっこよかったです(特にアインクラッド編とマザーズロザリオ編は素晴らしい)。
今年9月に上映予定のオリジナル劇場アニメ「HELLO WORLD」の制作で手一杯だったのは分かりますが、できればSAOシリーズは最後まで伊藤監督に手掛けてほしかったです。
次回につづく…










コメント
個人の感想なのであまり言いたくはないけど、原作は原作のよさが、アニメではアニメでの良さがあるので、そこまで原作に囚われない方が良いと思います。アニメは綺麗な映像描写でしたし、監督さんが変わった?のなら、最初の方はしょうがないと思います。
正直言って私も原作の方が好きで感動できる所がものすごいあるので、そこをアニメにも取り入れてほしかったって言う思いもあります。これの後のアリシゼーションwar of underworldの所はすっごい面白かったなと思います。
匿名さん、コメントありがとうございます。
そうですね。アニメにはアニメの良さが原作には原作の良さがあると思います。
ただ、これまでの伊藤監督が手がけたシリーズやアリシゼーションの原作が好きな自分には合わなかった、というか監督が視聴者に見せたいものと自分が見たかったものがあまりに違うかったので愚痴ってしまいました(笑)最初は本当に楽しみにしてたんですが。
途中で愚痴ばかりになってしまって感想を書くのを中断してしまいましたが、「War of Underworld」は作画や戦闘シーンの見せ方なども改善され、おそらく小野監督がやりたかったことであろうCGを駆使した大人数の戦いなど見所がたくさんありました。
心情描写を大胆にカットして子供でも楽しめるようにシンプルにつくったのは作品作りの方向性が定まった証拠なのかもしれませんね。